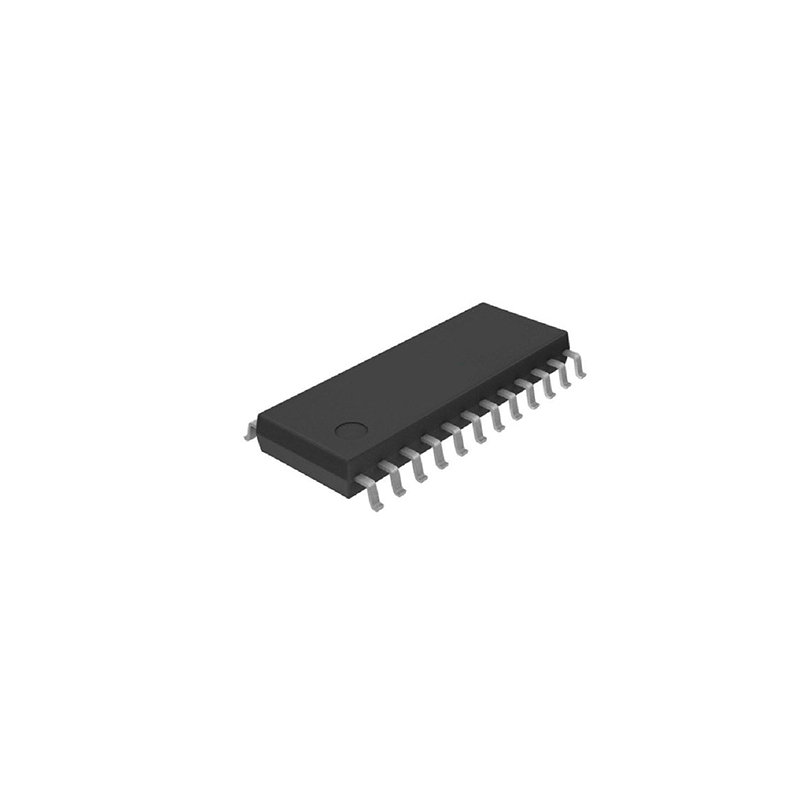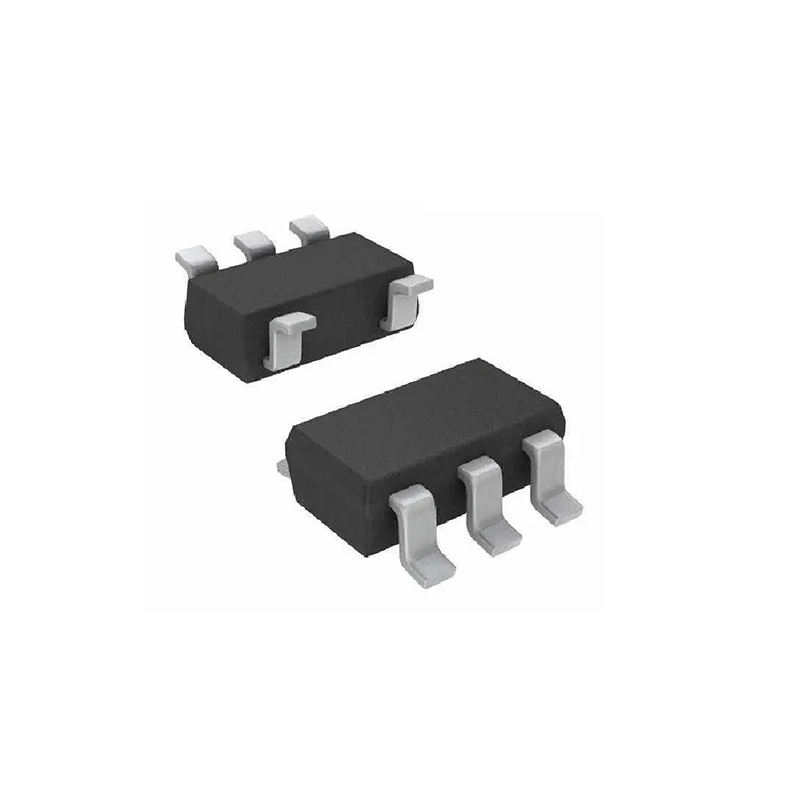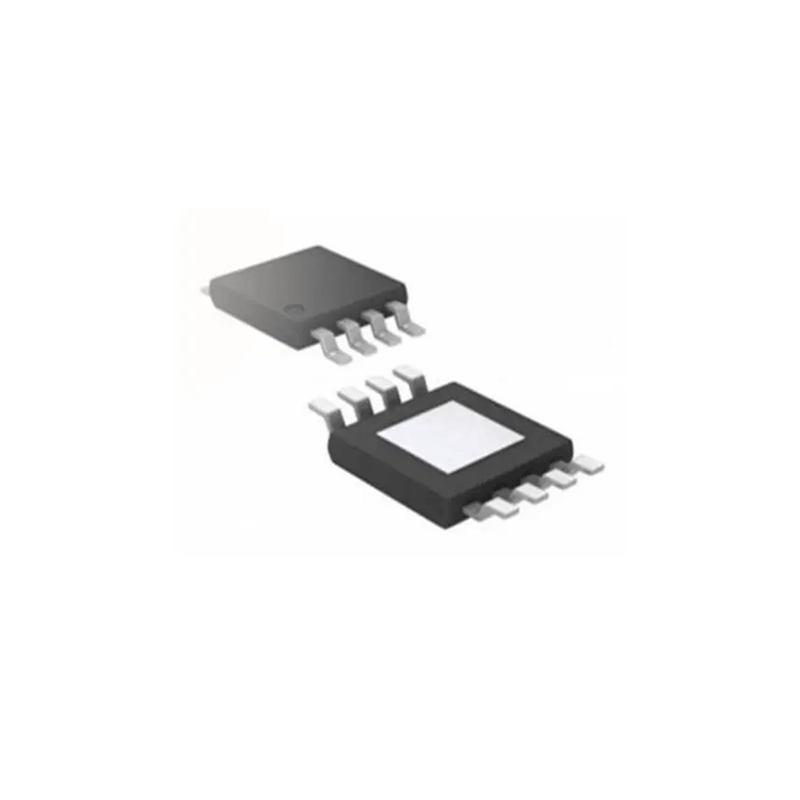はじめに
RS485回路は一般的なシリアル通信インターフェース規格で、産業制御環境で広く使用されている。平衡伝送と差動受信を採用し、コモンモード干渉を抑制する能力があり、通信距離は数十メートルから数千メートルに適しており、マルチノードシステムで優れた性能を発揮します。
産業制御の分野では、RS485バスは、センサ、アクチュエータなどの様々なデバイスを接続するためによく使用されます。差動伝送モードを通じて、RS485バスは効果的に安定したデータ伝送を確保するために、コモンモードの干渉に抵抗することができます。また、RS485回路は、絶縁デバイスを介してシステム電源とトランシーバ電源を絶縁することができ、システムの安定性と安全性をさらに向上させます。
SSP485チップは古典的な+5V低電力半二重RS485トランシーバーで、データ転送速度は最大2Mbpsです。+3.3V電源で、最大転送速度は500Kbpsを推奨します。SSP485は、+15kVESD静電気放電保護のフェイルセーフ回路を備えています。
SSP485レシーバは、単位負荷あたりの入力インピーダンスが1/8で、最大256個のトランシーバをバスに接続できます。主にRS-485/RS-422通信システムに使用されます。
SSP485チップのピン図は以下の通り:

(SSP485ピン図)
ピンの説明は以下の通り:

(ピン配列)
SSP485の回路図は以下の通り:

(SSP485回路図)
SSP485の典型的な回路 REとDEは一緒に接続され、MCUの制御ピンによって制御される。
- 制御信号がHighでRE論理が1の時、SSP485は送信可能になる:
TXがHighの時、出力AはHigh、出力BはLow、つまり出力485はロジック1となる;
TXがローの時、出力Aはロー、Bはハイ、つまり出力485の論理0となる。
- 制御信号がLowでRE論理が0の時、SSP485は受信可能である:
485バスでA-B≧-50mVの時、RXはハイとなりロジック1を受信する。
485バスでA-B≦-200mVの時、RXはLowで論理0を受信する。
オプトカプラ絶縁回路

(絶縁回路図)
VCC_MCUとVCC2は、信号の絶縁伝送を達成するために光結合絶縁を介して、非共通電源の2つのグループであり、SSP485とMCUは共通ではなく、完全に絶縁され、効果的に高いコモンモード電圧の発生を抑制するため、大幅に485チップの損傷率を低減し、システムの安定性を向上させます。しかし、多くの回路デバイス、短寿命、コモンモードに弱い耐性、高い消費電力、伝送速度は、光電デバイスなどによって制限されています。
デジタル絶縁回路

(絶縁回路図)
自動トランシーバー回路

(回路図)
自動トランシーバー回路は、485回路の上に典型的な三極スイッチング回路を追加する。
- データ送信
データ0x72を送信したい場合、2進数の0x01110010と書き、TXピンは1と0を反映するようにHighとLowになる。
TXピンが0の時、トランジスタはオンしておらず、DEはハイとなり、ドライバ状態になる。DI端子が接地されている場合、AB間の差動レベル論理は0となる;
TX端子が1の時、トランジスタはオン、REはローで受信状態になり、A端子とB端子はプルアップ抵抗Ra2とプルダウン抵抗Rb2の働きでハイインピーダンス状態になり、AB間の差動レベル論理は1になる。
- 受信データ
データ受信時はMCUのRXピンを使用します。データ受信時、TXピンはHighのまま、トランジスタはON、REはLowとなり、受信状態になります。RXピンはAB端から送信されたデータを受信します。
トランジスタのオン遅延はnsレベル、オフ遅延はusレベルであるため、トランシーバ回路のローレベルの遅延時間が長くなり、その後に続くハイレベルの伝送は、外付けのプルアップ抵抗とプルダウン抵抗によって駆動され、抵抗値が高いほど立ち上がりエッジが遅くなる。



TXピンで送信されたビットが0で、送信されるビットが1であると仮定すると、外部プルダウン抵抗によって送信のハイレベルが駆動されるため、トランシーバは受信状態に切り替わる。ABラインがLowからHighに切り替わるには数百nsかかり、この間RXピンは0を受信する。ボーレートが高すぎると、RX端子が受信したLowレベルを受信開始ビットと勘違いしてしまい、異常通信となる。従って、実際の回路を測定し、128000bps以下の自動トランシーバレートであれば正常な通信が可能です。
_画板-1@2x.png)